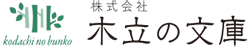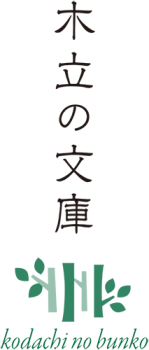どうやって本を作ろう
11 他者と巡りあうチャンス(後編)
確かに大学のゼミや学会の発表では、同じ関心を有している仲間と話をします。ですから、学界用語や仲間内のジャーゴンを知らないほうが「不勉強だ」と怒られてしまうくらいですので、話をするほうは楽といえば楽ですよね。みんなの共通理解(私に言わせれば「たちの悪い常識」)に寄り掛かっていれば、ある程度、会話が成り立ってしまうのですから。
ところが、安全に包まれた学界(身内)の外に一歩足を踏み出すと、自分の使う常識を共有しない“他者”に囲まれます。じつは、この白紙の(常識を共有できない)状況こそが、本を書くうえで実に大切なものなのです。自分の言葉が通用しない読者に囲まれている。その感覚があるからこそ、遠くまで言葉が届くように、一生懸命その言葉を説明しようとするのです。
伝わらない“不安”を本人が抱えていなければ、実際には、その人の言葉は決して伝わりません。自分の属する狭い「業界語」を、違う業界の人にしゃべっているわけですから、伝わるわけがありません。
――ここまで前編
“他者”にどう向き合うか。
そこで私たちは、自分の住む世界の狭さに始めて気づき、その限界を乗り越えるために、それまで自分が「当たり前」だと思い込んできた自分の使う言葉を一つひとつ「対象」化させていくのです。そのなかで、自分にとっての常識は、先生や格好よい先輩が使っていたから真似していただけで、自分では何ら吟味したことのない「もの真似」の言葉に過ぎなかった、と気づくこともあるでしょう。
残念ながら、自分の狭い寝ぐらに戻り、二度と出てこない人もいます。「めんどくさい」と言って。しかし、そういう人は、本当の意味での学者ではないと思うのです。「学んで問う」、すなわち学問という言葉の由来にふさわしい学ぶ姿勢を放棄してしまったわけですから。

「村上春樹とポスト福島における民主主義を問う」
Divinity School
(2014年)
大きな学会や異なる分野の学界で、学閥を異にする人たちへの研究発表、カルチャーセンターなど、一般の方への講演、さまざまな外国での報告会……。できれば日本語が分かる人がほとんどいない会場のほうが、経験を積むのには望ましいです。徹底して孤独な状態に置かれますから。
私の場合でいえば、韓国のソウルで、高卒の人たちを相手に自分の生い立ちを話して、必ずしも大学に行かなくてもできる学問の話をしたときが、もっともハードな経験でした。韓国語の通訳を通して日本語で語ったのですが、ハーバード大学で英語の授業をするよりも、はるかに緊張と責任を感じました。
こうした経験は、“他者”との出会いを準備してくれる宝物のような時間に、私たちを連れて行ってくれます。もちろん、同じ主題でも、発表の内容はどんどん変わっていきます。自分自身の暗黙の前提としている「常識」がどんどん崩れ落ちて、書き直されていくからです。パワー・ポイントの写真も引用文も入れ替わっていくのです。
繰り返し同じ主題のもとに講演をして、内容を手直ししていくことで、講演は成熟していくとともに、見違えるような変貌を遂げていくのです。このように、本を書くためには「反復」が不可欠な経験なのです。
上記写真の講演をYoutubeで観る
【どうやって本を作ろう】 12につづく
磯前順一(いそまえ・じゅんいち)
1961年、水戸生まれ(いまは水戸と京都を往ったり来たり)。1991年、東京大学大学院博士課程(宗教学)中退。東京大学文学部助手、日本女子大学助教授を経て、2015年より、国際日本文化研究センター研究部教授。文学博士。
著書は『土偶と仮面――縄文社会の宗教構造』〔1994年〕以来、多数。近著に『ザ・タイガース――世界はボクらを待っていた』〔2013年〕、『死者たちのざわめき――被災地信仰論』〔2015年〕、『昭和・平成精神史――「終わらない戦後」と「幸せな日本人」』〔2019年〕など。
-1024x768.jpg)