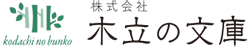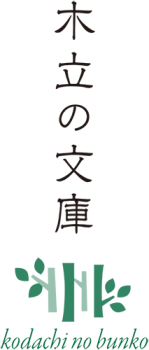どうやって本を作ろう
10 他者と巡りあうチャンス(前編)
ときどき聞かれることがあります――『これから初めて本を書く自分は、知名度などないですよね。どうやったら講演をする機会を手に入れられるでしょう?』と。
おっしゃるとおりです。少し説明しましょう。講演(lecture)と云いましたが、私が言いたいのは“トークの機会”のようなものです。トークとは、非公式な場を含めた「お話」の機会ですね。聞き手は友人でも、ゼミや研究会の仲間でもいいんです。なぁなぁにならないように、お互いに緊張感をもって臨む約束さえしておけば。ただ、面識のない人の前で話す講演の類が、いちばん緊張感が高く、本づくりには理想的な環境になるので、代表して「講演」と言っているだけなのです。
話者に対する「ほどよい関心」と、話者と聴き手のあいだに漂う「適度な緊張感」。それが、話すときに醸し出されるように心がけておければ、話をする場の設定としては言うことはありません。
私の知名度などは一部の宗教学や日本研究の分野でしか通用しませんから、一般向けの大規模の講演会では。「誰、この人?」という程度の期待しかされていません。多くの場合、こうした私のように、聞き手の関心は、話し手その人にというよりも、その「主題」や「主催団体」に向けられている場合が多いものです。つまり、講演が始まる前までは、私に対する関心は白紙です。それをどのように持っていくかは、私の話す内容と話いかんにかかっているのです。
その時に、話し手が「自分ことはみんな知っているんだろう」「自分に対して好意を持ってくれるだろう」と、友達・親戚に向かって話している感覚で話し始めると、かえって反発を買うことになるでしょう。自分のことを他人が知っていて当然なのではなく、「知らない」ことを前提にして話を始めるべきなのです。聞き手は自分のことを熟知している身内ではありません。むしろ、自分のことを知る手掛かりが与えられいない「他者」なのです。逆にいえば、知らないからこそ、「未知の期」を携えて来場してくれたのですよ。

Center for International & Global Studies
2019年12月4日
確かに大学のゼミや学会の発表では、同じ関心を有している仲間と話をします。ですから、学界用語や仲間内のジャーゴンを知らないほうが「不勉強だ」と怒られてしまうくらいですので、話をするほうは楽といえば楽ですよね。みんなの共通理解(私に言わせれば「たちの悪い常識」)に寄り掛かっていれば、ある程度、会話が成り立ってしまうのですから。
ところが、安全に包まれた学界(身内)の外に一歩足を踏み出すと、自分の使う常識を共有しない“他者”に囲まれます。じつは、この白紙の(常識を共有できない)状況こそが、本を書くうえで実に大切なものなのです。自分の言葉が通用しない読者に囲まれている。その感覚があるからこそ、遠くまで言葉が届くように、一生懸命その言葉を説明しようとするのです。
伝わらない“不安”を本人が抱えていなければ、実際には、その人の言葉は決して伝わりません。自分の属する狭い「業界語」を、違う業界の人にしゃべっているわけですから、伝わるわけがありません。
【どうやって本を作ろう】 11につづく
磯前順一(いそまえ・じゅんいち)
1961年、水戸生まれ(いまは水戸と京都を往ったり来たり)。1991年、東京大学大学院博士課程(宗教学)中退。東京大学文学部助手、日本女子大学助教授を経て、2015年より、国際日本文化研究センター研究部教授。文学博士。
著書は『土偶と仮面――縄文社会の宗教構造』〔1994年〕以来、多数。近著に『ザ・タイガース――世界はボクらを待っていた』〔2013年〕、『死者たちのざわめき――被災地信仰論』〔2015年〕、『昭和・平成精神史――「終わらない戦後」と「幸せな日本人」』〔2019年〕など。
-1024x768.jpg)