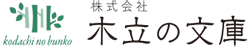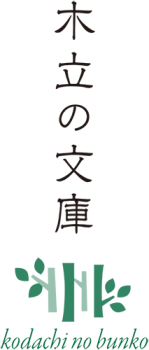みんなのひきこもり【終了】
そもそも「ひきこもり」とは?
[加藤隆弘]
ひきこもりの歴史を紐解いてみましょう。
ひきこもりが「ひきこもり」という言葉で注目されはじめたのは1990年代後半からです。しかし、数ヵ月にわたり学校に行かず、仕事に行かず、一日中自宅にいる人(あるいはそうした状況のこと)を、わたしたち日本人は「ひきこもり」と、ずいぶん昔から称してきたのではないでしょうか。
いつ頃から「ひきこもり」という言葉が使われるようになったかは定かではありませんが、「ひきこもり」という現象はすでに80年代に私が中学生だった頃には存在していたと思うのです。当時、『○○君の弟、ずっとひきこもって学校に行っていないんだって』というような形で「ひきこもる」という言葉を使っていたように記憶しています、いわゆる不登校のことです。
実際には、「ひきこもり」が現在のように名詞として使われるようになったのは、精神科医・精神病理学者である斎藤環氏の『社会的ひきこもり――終わらない思春期』(PHP新書 1998年)が出版されてからではないでしょうか。
90年代後半といえば、私は不肖の医学生真っ只中でした。運動部で自分のメンタルの弱さに直面し、骨折を機に退部して若干こころも折れて、「巣ごもり(?)」あるいは「プチひきこもり(?)」的な生活を送っていたのです。久しぶりに登校した大学の帰り道、生協に立ち寄った際にこの新書が陳列されていたことをなんとなく覚えています。ただし、「これは自分のことじゃないか?!」とまで思ったかどうかは記憶にありません。当時、プチひきこもり生活を送りつつ、春休みや夏休みにはさらに孤独を強いられる一人旅に出かけていたのでした。
斎藤環氏は「社会的ひきこもり」を「二十代後半までに問題化し、6ヵ月以上、自宅にひきこもって社会参加をしない状態が持続しており、ほかの精神障害がその第一の原因とは考えにくいもの」と定義しました。「6ヵ月以上、自宅にひきこもって社会参加をしない状態が持続」、これが何より重要な点ですが、曖昧でもあります。「学生という身分があるから、社会参加していないわけではないぞ!」という言い訳もいえるわけで……と、当時の私を振り返るのです。
こういう場合はどうでしょう?
社会人になった子どもが上京し、数年後不景気になり退職。実家にもどり、ひっそりと自室にこもり昼間は一切外に出なくなった息子・娘に対して「我が子は精神疾患かもしれない?!」という不安や恐怖を多くの家族は抱きつつ、「いやいや、会社で嫌なことがあったから、その挫折で傷ついているだけ(と信じよう)。しばらくしたら以前のように元気になってくれるはず。ひきこもりは精神疾患が原因とは考えにくいみたいだし」という具合に考えてしまうのは、自然の成り行きでしょう。人間には万事ものごとを楽観的に捉えようという癖が備わっています。
この癖のおかげで、私たちは多少の困難がありながらも、一喜一憂しすぎずに日常生活を送ることが出来るのです。ちなみに、この癖をもっていない場合には、うつ病や不安症になりやすいのかもしれません。
実際には、ひきこもり者が精神疾患を並存することは稀ではないということが、次第にわかってきました。たとえば、児童精神科医である近藤直司氏による精神保健福祉センターでの調査では、ひきこもり者に統合失調症、うつ病、発達障害といったさまざまな精神疾患を並存していたという結果が得られています。
こうした背景をもとにして、2010年に厚労省から「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」〔研究代表者: 齊藤万比古氏〕が発行されました。
このガイドラインでは、ひきこもりの要因として、心理社会的要因や生物学的要因をあげており、生物―心理―社会モデルに立脚した支援アプローチの重要性を唱えています。そして、「原則として統合失調症は含まないもののその可能性も否定できない」としており、ひきこもり者に精神疾患の並存が稀ではないと宣言したという点で、このガイドラインは画期的でした。
このガイドラインにより、ひきこもり支援は次のステージに進みましたが、ガイドラインだけでひきこもり問題が抜本的に解決したかというと、必ずしもそうではありません。いまだにひきこもり者の評価や支援は難しいのです。次回、その打開のために、わたしたちが取り組んできた研究をひとつ紹介します。
マスター
加藤隆弘(かとう・ たかひろ)
九州大学病院 精神科神経科 講師
日本精神神経学会専門医・指導医、精神保健指定医
共著『北山理論の発見』(創元社 2015年)など
●参考Web記事のURL https://www.data-max.co.jp/article/21378?rct=health