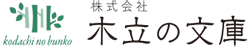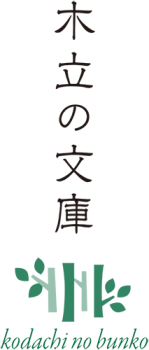こころとからだの交差点【終了】
心身医学における諸問題
[岡田暁宜]
第七話ということで、徐々にリレーらしくなってきたように思う。
第六話で磯野先生は、敬称を「先生」から「さん」へと変えておられる。私は、以前に経験した力動的集団精神療法のことを思い出した。私が参加した力動的集団精神療法には、老若男女のほかに他職種のメンバーが参加し、そのなかでは、互いに「さん」で呼び合っていた。本リレーエッセイにおいても、さまざまな集団力動が起きているのかも知れない。医師には、互いに相手を「先生」と呼び合う文化があり、私にはかなり馴染みがあるが、それ自体が防衛的な意味をもつこともある。
大先輩である「齋藤先生」を「齋藤さん」と呼ぶことに若干の抵抗感はあるが、今回の磯野先生の変化に私も合流するのが自然であると思う。よって、第七話から、私もお二人の呼称を「さん」とさせていただくことにする。
心身医療における「覆い」と「捻れ」
第五話において齋藤さんは「『心身』という言葉に違和感はあまりなかったが『心身症』という言葉には違和感がかなりあった」と述べている。私は今でも「心身」という言葉にも「心身症」という言葉にもあまり違和感はない。
齋藤さんは“心身症”という言葉に対する違和感についての説明において「心身症という概念がほぼ消滅している」と述べている。そこで1991年の日本心身医学会による心身症の定義に言及し、この定義は1996年に設立した日本心療内科学会の心療内科の在り方を決定づけることになったという。さらに1991年の日本心身医学会の「心身医学の新しい診療指針」における心身症の定義について、ふたつの問題を示している。ひとつは「本定義では、心身症を身体疾患に限定し、神経症やうつ病に伴う身体症状を除外した」ことであり、もうひとつは「本定義における心身症の患者が心療内科を訪れることはほとんどない」ということである。齋藤さんは、心療内科を訪れる身体症状を訴える患者の大半は、器質的な異常を伴わない機能性身体症候群 functional somatic syndromeであり、そのほとんどは臓器別診療科や総合診療科でケアされているという。
以上の齋藤さんの見解について、私はまったく同感で、まったく異論はない。
さらに齋藤さんは「精神疾患としての心身症」の節で、「今日、心療内科を訪れる患者の大半は、DSM-IVでいう〈身体表現性障害〉、DSM-5でいう〈身体症状症 somatic symptom disorder〉であり、心療内科では『身体の病気がないのに身体症状を呈する精神疾患』を診ている」というように述べている。
これらの見解についても私はまったく同感である。私が勤務している診療所は、精神科の他に心療内科も標榜しているが、初診の患者のなかには、心療内科だと思って受診する者も少なくない。今日の臨床現場において精神科医が「心療内科」という診療科を積極的に標榜する理由として「神経科」や「心療科」と同様に「精神科」への敷居を下げるためだけでなく、「精神科」という診療科を覆い隠すこともあるように思われるが、それは、おそらく患者のニーズを汲み取ったものであろう。
実状を見る限り、心療内科は、身体医学的に説明できない症状 medically unexplained symptomsを呈する患者のなかで精神科やこころの問題に抵抗のある患者の受け皿になっているといえるだろう。
この点については、私は日本における心身医学運動の理念に立ち戻り、1970年の日本精神身体医学会〔現: 日本心身医学会〕の「心身症の治療指針」にまで遡る必要があると考えている。1970年の心身症の治療指針では《身体症状を主とするが、その診断や治療に、心理的因子についての配慮が特に重要な意味を持つ病態》と心身症を定義している。そこでは《身体的原因によって発生した疾患でも、その経過に心理的な因子が重要な役割を演じている症例や、一般に神経症とされているものであっても、身体症状を主とする症例は広義の心身症として取り扱ったほうが好都合のこともある》と記述されている。1970年の心身症の定義は、1991年のような心身症を精神疾患と区別する診断的視点からの定義ではなく、治療的視点からの定義といえるだろう。心身医療の理念は、1970年の心身症の治療指針にあると私は考えている。心身医療の視点に立てば、1970年の心身症の定義に回帰する必要があるのではないだろうか。
齋藤さんは、第五話で「それでは誰が心身症を弔うのか?」という問いを投げかけている。
私は“心身症”臨床の現状について、次のように考えている。“心身症”の概念は多義性であり、1991年の定義でいう狭義の心身症を実際に診ているのは、臓器別診療科のいわゆる身体科といえるだろう。1970年の定義でいう広義の心身症を診るのは、本来であれば、精神科であるが、心の問題や精神科への抵抗を示す患者の受け皿として心療内科が一定の役割を果たしているであろう。
そのうえで、次のような現象が起きていると考えている。それは、私が「心身医療と心療内科の捻れ現象」と呼ぶ現象である。それに向けて、まず私の立場をあらためて明確にする必要があるだろう。私は1991年に医師になり、同年に日本心身医学会に入会し、1970年の日本精神身体医学会〔現: 日本心身医学会〕の“心身症”の定義に賛同し、心身医学運動として心身医療の実践を始めた。1996年に日本心身医学会の認定医試験を受けて、認定医となり、その後、専門医となった。1996年は、アレルギー科、リウマチ科、リハビリテーション科などとともに《心療内科》が新たに標榜診療科として認可された年であり、日本心療内科学会が設立した年でもあった。しかし私は次のような理由で、日本心療内科学会に入会していない。
その理由は「心身医療と心療内科の捻れ現象」という理解に至った私が心身医学運動として心身医療をおこなううえで《心療内科》という診療科に臨床的な矛盾を感じためである。もうひとつの理由は、私が心身医学の源流である“精神分析”の道に進むことを決意したことがある。
私にとって心身医学とは、すべての診療科において意味のある普遍的な医学モデルを提示する学問であり、心身医療とは、すべての診療科において、実践できる/実践すべき医療であった。少なくとも当時の私には、日本心身医学会の内科医のみが中心となった日本心療内科学会 Japanese Society of Psychosomatic Internal Medicineは、他の診療科の医師や他の職種が排除されているように見えていたし、心療内科の理念と心身医療の理念が捻れているように見えたのである。
その一方で、日本心療内科学会の設立の背景についても考える必要があるだろう。
1977年にG・エンゲルが提唱した「生物的心理的社会的」医学モデルの後、日本における心身医学運動において心身医療が社会的に認知されるために、心身医学は、医療のなかに居場所を確保することが必要であったように私は思う。そして既存の社会的な枠組である、大学医学部における講座や医局、あるいは病院や診療所における標榜診療科に心身医学の居場所を求めたのだろう。そのような背景のなかで誕生した心療内科医を束ねる学会が日本心療内科学会であるように私は思う。それは心身医学運動の歴史のなかで、ある意味でやむを得ない戦略や過程といえるかも知れない。
しかし、心身医学を実践する本来の心身医療は、縦割的に並存する従来の診療科に対して横断的に跨がる概念であったはずであるが、《心療内科》を標榜することによって、縦割的に並存する従来の診療科のなかに組み込まれてしまったのではないだろうか。それが「心身医療と心療内科の捻れ現象」と私が呼ぶ現象である。
さらに《心療内科》誕生の背景には、心身医学を実践する心身医療に携わる専門家たちの臨床的アイデンティティの問題があったように、私は思う。心身医学や心身医療に携わる専門家のアイデンティティの問題と“心身症”で苦しむ患者のアイデンティティの問題は力動的な共通点があるように私は思う。
心療内科にとって重要な年となった1996年頃、私は実は次のようなことを考えていた。すべての診療科において、心身医学を視野に入れた心身医療が適切におこなわれるならば、すべての診療科は、象徴としての《心療内科》と言えるのかもしれない。さらに、すべての診療科が従来の縦割りから脱却し、患者中心に連携して、狭義から広義の心身症を医療全体で抱えることが可能になり、さらに社会-文化的なレベルで人間のなかにある“心”の問題や精神科への抵抗が軽減してゆけば、《心療内科》という診療科は不要になるのではないだろうか。このような考えは、当時の私が抱いていた《心療内科》をめぐる幻想であるが、当時の私自身の治療者としての葛藤と無関係ではないだろう。
これに関連して、医師の専門性をめぐる最近のトピックに、日本専門医機構による専門医とそのサブスペシャリティ領域をめぐる議論がある。日本心身医学会と日本心療内科学会は、基本領域を内科とするサブスペシャルティ領域の専門医制度を新たに発足した。専門医の名称は、心療内科専門医である。しかし内科専門医のサブスペシャリティを目指す心療内科専門医は、1970年の定義にある心身医療の基本理念を保持できるのかどうか、今後の行方を見守る必要があるだろう。じつはサブスペシャリティをめぐる問題は、精神分析が精神科専門医のサブスペシャリティとして認められるかどうかという問題とも密接に関連している。

異文化へと開かれること
第六話で磯野さんは、文化人類学者の立場から“心”に向けてさらに考えを広げている。そこには、文化人類学からみた精神分析への問いが含まれている。
「精神分析家はたとえ爆弾が落ちてくるような状況であっても分析をしている」というのは、精神分析家の分析的態度に対するひとつの比喩といえるだろう。しかし実際に爆弾が落ちてくる戦地では、“心”に向けた精神分析をおこなうよりも、まずは身体の安全を確保することが、心身の両面において大切であると思う。実際に精神分析では、内的環境のみならず、外的環境も重視しているように思う。精神分析は、精神分析という理念に基づく精神分析学といえるかも知れないが、一方で、精神医学とは異なる独自の世界観を有しているといえるだろう。
身体と世界の接点に“心”を見ようとする磯野さんは、「身体とはそれ自体が心ではないか」と思うことがあったようである。文化人類学は、身体が心そのものを表す力動的な状況を捉えているのかもしれない。文化人類学に独自の学問文化があるように、精神分析にも独自の文化がある。異文化間交流では、自分の言葉と相手の言葉の違いを知ることが大切である。その意味で、磯野さんが言われるように、同じ言葉を同じ理解のうえで用いるのではなく、互いの立場を明確にする自分の言葉を使用した方がよいのかもしれない。いずれにしても、「異文化交流」自体にこのリレーエッセイのエッセンスがあるので、異なる領域や専門性と交流し、馴染みのない現象や素材をみずからの言葉で理解して、相手に伝えることが大切なのかもしれない。
興味深いことに、精神分析と哲学は、人類学と関係の深い領域であり、一度踏み込んだら出てこられなくなる可能性について、磯野さんは示唆している。ある領域で何かを極めるということと、別の領域と交わって何かを発見するということに、臨床家は葛藤を抱くかもしれない。それこそ私が以前に感じた「心の専門家」と「身体の専門家」の関係性を表しているように思う。
磯野さんは、最近、新たに向き合った書物としてC・G・ユングの「分析心理学セミナー」を挙げて、そこに書かれている、アクティヴ・イマジネーション/能動的想像法とその例を示してくださった。ユングについては、私よりも齋藤さんの方が詳しいわけであるが、私にとっては、精神分析における自由連想法 free association methodとの類似点と相違点を考える機会になった。アクティヴ・イマジネーション法では、例えば、ヘビという姿が心に浮かんだら、ヘビに対して受身的に身を委ねて積極的に関わり、無意識との対話を重ねるようである。ユングが重視したのが普遍的な無意識 collective unconsciousであるのに対して、精神分析が重視しているのは被分析者の個人的な無意識 personal unconsciousであるという点が、アクティヴ・イマジネーション法と自由連想法の違いといえるだろう。普遍的無意識を重視しているという点で、文化人類学はユングの分析心理学と共通点があるのだろう。
ユングのアクティヴ・イマジネーション法に対して磯野さんが最初に連想したものが、シャーマンのおこなう呪術であるようである。磯野さんは、精神分析と呪術を分けるものは何か? と、新たな問いを私に投げかけている。この問いは、私にとってある意味で興味深い問いであった。
この問いを受けて、私は自分が二年程前まで勤めていた大学のことを思い出した。
当時、私は大学教員としては人文学部に所属しており、同じ学部には、人間の普遍的な本質に迫ることを目指した人類文化学科があり、そこには文化人類学を専門にする先生方がおられた。今から思えば、同じ学部でありながら、文化人類学の先生方との学術的な交流はまったくなかったことに、私はあらためて気づいたのである。当時の私の治療者としての心は、保健センターという医者の文化のなかに閉ざされていたのであろう。もちろん S・フロイトがみずからの精神分析を論じるうえで呪術やシャーマニズムにもしばしば言及していることは知っていたが、私にとっては、自分が実践している精神分析は、もはや呪術と比較するようなものではなかったのである。おそらく私は、接点がないほどに精神分析と呪術を分け隔てていたようである。
せっかくの機会であるので、精神分析と呪術との違いについてあらためて考えてみたい。ただし、私は呪術というものを実際に見たことがないので、あくまで想像上の呪術ということになる。呪術とは、呪術師は神や精霊などの超自然的で神秘的な存在に働きかけて、患者の願いを叶える方法といえるだろう。これに対して、精神分析家が患者の無意識のなかに潜む「神」や「悪魔」を呼び覚ますという点、さらには、患者が精神分析家を「神」や「悪魔」を呼び覚ます「魔術師」の如く、あるいは精神分析家そのものを「神」や「悪魔」のように体験するという点において、精神分析は呪術と共通点があるかも知れない。
最早期の乳幼児の体験を比喩で言えば、母親は「神」であり「悪魔」でもあるといえるかも知れない。しかしながら、精神分析(家)は呪術(師)ではない。私が思うに、精神分析は人間による人間のための実践であり、決して「神」や「悪魔」の力を借りているわけではない。そのため精神分析には、常に限界というものがあり、精神分析家はみずからの無力さというものに耐えなければならないだろう。
C・G・ユングのアクティヴ・イマジネーション法は、適当におこなうと危険なので、きちんと訓練された専門家とともにやるべきであるということであるが、その点は、精神分析の実践と基本的に同じである。精神分析の訓練を通じて、今日の臨床倫理の上に実践されるという点は、呪術との違いといえるかも知れない。
磯野さんは、第六話の終わりに、最近のトッピックとして Human Papilloma virus (HPV)の副作用 * における心身問題について言及している。私は、HPVワクチン接種後の副作用とみられる方を直接診察した経験がないので、公表されている以上の知見をもっていない。
2015年に日本医師会が発表した『HPVワクチン接種後に生じた症状に対する診療の手引き』には、「『心因』という言葉が、器質的な病態の存在を全否定し、詐病的あるいは恣意的であると誤解されやすい事から、患者・家族も認める明らかな精神的問題を認める特殊な場合を除き、『心因』という表現は用いない」と明記されている。これらの内容は、精神科医の立場からみて、妥当であると思う。おそらく磯野さんが述べるような意見が社会のなかで存在するために、上記のような文言が診療の手引きのなかに設けられたのではないだろうか。いずれにしても、身体症状で苦しむ人々に対して心因性であると診断する行為自体がいかに暴力的であるかを、磯野さんは示しているだろう。
私は研修医の頃に経験した慢性疲労症候群 chronic fatigue syndromeという病態に対しても同様の精神力動を感じる。 psychogenicつまり心因性ということと、psychosomaticつまり心身相関があるということは、異なるのである。磯野さんが述べたHPVワクチンの副作用は心因性であるというひとつの社会的な見解に見られる暴力性は、「個別性の高い個体内の問題を社会-文化的なレベルで理解することの難しさ」を表しているように私は思うのである。
精神分析における理解は、基本的に“生きた人間”に対する関与しながらの観察に基づいているが、文化人類学における理解も基本的に同じであると私は理解している。
そのうえで、本稿において、私は社会-文化的なレベルで人間のなかにある“心”の問題や精神科への抵抗が軽減してゆくことについて触れたが、文化人類学では、観察による理解に基づいて、社会や文化に対して、どのような介入をしていくのだろうか。これは主に個人的な無意識を対象する精神分析からの問いであり、ひとつの期待でもある。
* 2010年頃より、子宮頸がんの成因とされる Human Papilloma virus (HPV) の感染予防として子宮頸がんワクチンが10代の女性を中心に接種されるようになった。その後、HPVワクチン接種後の副作用が報告されたことで、2013年にはワクチンの積極的勧奨が中止され、現在ワクチン接種率は大きく低下している。
マスター
岡田暁宜(おかだ・あきよし)
名古屋工業大学保健センター教授
1967年生まれ、名古屋市立大学大学院医学研究科修了、医学博士
愛知教育大学准教授、南山大学教授を経て現職
精神分析協会正会員
2010年、精神分析学会山村賞受賞