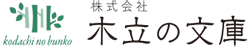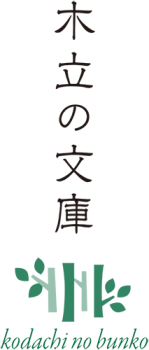いまここ日記【終了】
非常識らしさの発想2
[藤中隆久]
想定無用“いま”のリアル
~前回からの続き~
文楽の人形遣いの桐竹勘十郎は、内田樹との対談のなかで、稽古に関して次のような発言をしている。
「僕は、最近冗談半分で稽古なんかしても無駄だからって言ってるんです。だって、舞台稽古を何日もやっても、ただの段取り稽古でしかない。(略)うちの師匠は、ものすごく段取りが嫌いで、『段取り芝居ほどつまらないものはない』とおっしゃっている。だから、ぶっつけ本番大賛成。」
これを読んで「文楽の人形遣いなんて“ぶっつけ本番”が通用するお気楽な世界なんだ」と思ったらそれは、そう思った人のほうがお気楽なのだ。文楽は決してお気楽な世界ではない。何十年もかけて弟子修行をしながら芸を高めてゆく、きわめて厳しい伝統芸能である。
文楽は、真ん中の主遣い、右の足遣い、左の左遣いの三人が一体の人形に、舞台で語られている浄瑠璃のストーリーを演じさせる芸能である。三人で一体の人形を動かし、まるで人間のような動きをさせるのである。人形の体と手と足がバラバラにならないよう三人で一体の動きが出来なければいけない。しかも、人形遣い同士は言葉で意思疎通はできないので、三人の動きをお互いに感じながら、無言で意思疎通をしながら、人形に一体の動きをさせるのである。言葉を使わずに感覚だけで相手の意図を感じる訓練が必要である。俗に「足遣い十年」といわれていて、人形の足を体と連動させて動かせるようになるまでに十年はかかる、ということなのである。
前述の勘十郎は、足遣いを15年やったとのことである。このときの訓練は、いまここを感じることに尽きる。ぶっつけ本番の舞台という緊迫した状況のなかでいまここをリアルに感じることが、すなわち訓練となる。それぞれの人形遣いが人形の体感をいまここで共有し、それぞれが、その感覚に問いかけ続けながら人形を動かせば、そのとき、自然に人形の体と腕と足が一体となって、お芝居のシーンと調和のとれた動きとなっているはずである。つまり、人形遣いはいまここの感覚に照合しながら動くことがもっとも大切である。段取り稽古ばかりやると、いまここの「照合する感覚」は鈍化してゆく。

僕は面接で、受験生といまここの会話をしたいのだ。受験生には質問に対して、いまここで感じたことを答えてほしいのだ。面接官の問いに対して、想定してきた答えを思い出しながら、よどみなくスラスラと答えようとする意識は、「いまここで自分が感じたことを言葉として紡いでこうとする思考」の妨げになるはずだ。人間同士の会話は、ちょっとした言葉のニュアンスで、受け止め方や感じ方は変わるはずだし、受け止め方が少しでも違えば、そこでまた何かを新たに感じるはずだ。そのような“やりとり”を、入試の面接という場で僕はしたいのだ。
試験官も面接がどのような方向に進むかは予測不能。だから、想定問答などは無意味。受験生としては、想定していない方向に会話が進むと不安になるかも知れないが、それこそが、面接の醍醐味なのだ。自分が想定していない方向に会話が進むと不安になって、それを圧迫面接と受け取るような人は、あまりに精神も頭脳も脆弱ではないだろうか。
受験生がいまここで考えた末に出した答えに対しては、当然、僕だって、ものすごく真剣に、いまここで感じたことを答えるだろう。そのような“やりとり”を繰り返してゆけば、ふたりのあいだに交わされる会話のクオリティはどんどん高まってゆくだろうし、そのような“やりとり”を繰り返してふたりの共同作業により到達した結論は、非常に説得力のあるものになっているはずだろうし、面接が終わったときには、ふたりともに、爽快な気分になっているだろう。
《どうして、我が大学を受験したんですか?》
『はい、まずは、教育実習制度の充実です。貴学では豊富な経験を段階的に積むことができるので、理論と実践の両面からしっかり学べると思ったからです。以上です。』
こんな会話は、僕はまったく望んではいない。
《どうして、我が大学を受験したんですか?》
『地元だし、偏差値的に受かりそうだから受験したんですが……。でも、今日来てみたら、面接官の先生方がみんな優秀で、イケメンで、わたしの受験の理由はコレだ! って、いま、思いました。』
僕は爽快な気分になって、思わず言ってしまうかもしれない――《もう、君、合格!!》(2019年1月8日)
マスター
藤中隆久(ふじなか・たかひさ)
1961年 京都市伏見区生まれ 格闘家として育つ
考えなおして1990年 京都教育大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)
九州に渡り1996年 九州大学大学院教育学研究科博士後期課程修了
南下して1999年から熊本大学教育学部 2015年から教授
推定5.8フィート 154ポンド