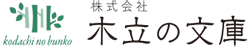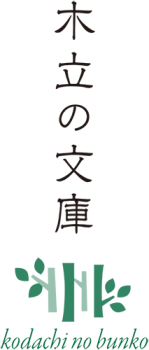こころとからだの交差点【終了】
心と身体の空間
[岡田暁宜]
リレーエッセイは、これで一巡したことになる。
これまでは、それぞれの著者による自己紹介といえるだろう。第1回の私と第2回の齋藤先生のエッセイを受けて、第3回で磯野先生から「問い」が投げかけられた。
ひとつのプロセスとして、今回は、磯野先生の問いから、私のなかの内的対話を進めたい。
「心身への違和感」から
「《心身》という言葉に違和感はないですか?」という純粋な問いを受けて、私は、自分が今まで《心身》という言葉に違和感をもっていなかったことに気づいた。そこには、私の臨床家としての出自があるだろう。私は《心身》という考えに親和性があるようである。
「心身」とも「身心」とも書くが、いずれにせよこれらは、こころと体が未だ分化していない乳幼児世界のような状態、あるいは、こころと体が容易に置き換わる力動性を表しているようである。見方あるいは状況によっては「心vs.身体」「心or身体」というように対立するかも知れないが、《心and身体》という一対の概念といえる。
日々の臨床において「こころとしてのからだ」や「からだとしてのこころ」という力動を経験することがある。このようなこころとからだの関係は、「こころと脳」の関係にも当てはまるかも知れない。経験的にこころとからだが互いに協働し補完し合う関係の場合もあれば、互いに支配や攻撃し合う関係の場合もある。
また見ようによっては《心身》という言葉には、「光影」「虚実」「陰陽」「表裏」「内外」「男女」「動静」「生死」などのような、互いに対立しながらも互いに必要とする二つの存在や関係に宿る、ある種の“うつくしさ”が感じられる。そのような美しさを私は「意識と無意識」にも感じる。少なくとも私が考える精神分析では、ただ無意識のみを扱っているわけではなく、《意識and無意識》の一対を扱っているのである。
こころは何処に
磯野先生が紹介してくださった、ライル〔Ryle, G.: 1900-1976〕が『デカルト神話』のなかで心身二元論への批判として用いた「機械のなかの幽霊のドグマ」や「高校を歩き回った結果、教師は見つかったが、校風は見つからなかった」という比喩は、おもしろい。
幽霊も校風も実体としては存在しないが、それらが恰も存在しているかのように、人間は生活している。幽霊を見るのも、校風を感じるのも、すべて人間のこころなのである。デカルトのコギトが思い出されるかも知れない。幽霊は、こころのなかの不安や恐怖の投影であり、居場所の定まらない存在を表しているだろうし、校風は、集団と歴史という学校文化のなかで育まれるものである。
現代医学は、精巧な機械や堅牢な校舎として概ね存在しているのかも知れないが、人間が機械を使用し、校舎で生活するなかで、そこに「こころ」が宿るのであろう。それは“世界観”といえるだろう。
齋藤先生が「胸や心臓のあたりには『胸がキュン』とする歓びや、『胸が締め付けられる』ような苦しさを感じる“こころ”があります」と述べたことは、こころは心身相関(情動身体反応)に裏づけられた心臓heart♡であることを示している。その意味で心臓はこころを象徴している。
心臓が象徴するものは、それだけではない。脳死の判定が可能になる以前は、心停止が人間の「死」の基準であった。その意味で心臓は“生命”を象徴している。心理臨床家はこころをいのちと等価に考えているのではないだろうか。
心臓がこころを象徴する理由は、心臓が体幹部の内部にあるからだと私は思う。「胸中」という言葉があるように、人間にとって“こころ”とは、内部・深層・中心という場所に局在するものである。「内心」という言葉があるように、人間が“こころ”に対して抱く心象は、中身のある容器のような構造を呈しているのではないだろうか。その意味で人間は心を「空間」や「場」と捉えているのではないだろうか。
心理臨床において、患者が述べる「空虚感」という言葉は、中身がない空洞のこころを指している。「中身」という言葉があるように、こころのなかには「身体」があるようである。これは「身体感覚としてのこころ」といえるだろう。「身につく」「身になる」という言葉は、言葉の上では「身体化」であるが、ここでの「身体」は“こころ”を象徴しているのである。
磯野先生は、世界との接合面に形を変えて現れる表現形式として“こころ”を捉えて、こころは「現れ」であると述べている。
我々は、今まで見えなかったものが見えるようになる際に「現れる」という言葉を用いる。そこに現れる“こころ”とは、外的現実からの要請に対するために、あるいは現実に適応するために、発動する反応といえるだろう。
一方で、こころのなかにあるものが姿を現す際には「表れる」という言葉を用いる。無意識が意識化して姿を現す過程は「表現」や「表出」と呼ばれる。これは、精神分析の基本といえるだろう。私にとっての“こころ”は、場所や空間であり、そこには現れない領域や表れない領域があり、そこに「大切なもの」や「恐ろしいもの」が存在しているのである。
こころの病気の名前
磯野先生はエッセイの終わりに、近年の「こころの病気」の増加への違和感として、「病気のラベルの増加」に言及している。この議論はとても重要である。
私は「精神医学的診断がいかに人間理解を妨げているか」という自分のなかにある考えを再認識させられた。今日の精神医学的診断が「病気のラベル」であるとすれば、それは“こころの中身”についての本質的な理解ではない。その意味において、今日の精神医学的診断は「精神医学との接合面に現れる表現形式」といえるかも知れない。磯野先生の「心の病気の増加」への違和感は「精神医学」への違和感を表しているようである。この違和感は、私も含めて、精神分析の臨床家が抱いている臨床感覚ではないだろうか。ラベルが理解を妨げる理由は、ラベルは対象物を整理するために対象物の表面に「付けるもの」あるいは「貼るもの」であり、それは、本質的に中身を覆う行為であるからである。

交差点に向かって
最後に、磯野先生が初めに述べた「事故は交差点で起こる」「交差点は危ない」という言葉に触れたいと思う。いま走り出しているリレーエッセイのタイトル【こころとからだの交差点】について考えれば、交差点における事故の危険性は、確かに考慮すべき事象といえるだろう。
そこで思い出されるのは、私の学生時代のひとつの交差点体験である。
現在、私が勤務する大学のすぐ近くにある、信号機のない見通しの悪い交差点で、私は自動車と自動車で出会頭事故をしたことがあった。不幸中の幸いで、互いの自動車の損害は板金修理で済む程度の損害で、事故の過失は5対5であった。今でもその交差点を通ると、その時の記憶が蘇るのである。
信号機のない見通しの悪い交差点で事故が起きる心理的理由は、その事故の可能性をドライバーが心理的に否認しているからであろう。
道路における交差点とは、二つ以上の道路が交わる場所であるが、安全に交差点を走行する車同士は、実際には、触れることはなく、すれ違っている。比喩としての「交差点」は“出会いの場”であり、交差する過程で相互に交流する“創造の場”でもある。
神経学者であったフロイト〔Freud. S.: 1895〕は、多くの不可解なヒステリー患者と出会い、その結果、精神分析が誕生した。そしてフロイトは、アニミズムやトーテミズムなどさまざまな民俗-文化的な論考をおこなっている〔1913〕。彼の著作は今日でも、臨床をおこなわない思想家や哲学者に幅広く愛読されている。その意味で、精神分析は“意識と無意識の交差点”の臨床であり、「異なる領域」や「異なる文化」との交差点の学問といえるだろう。
交差点としてのリレーエッセイを通じて、齋藤先生との出会い、磯野先生との出会いから、なにかを創造できればと思う。
マスター
岡田暁宜(おかだ・あきよし)
名古屋工業大学保健センター教授
1967年生まれ、名古屋市立大学大学院医学研究科修了、医学博士
愛知教育大学・准教授、南山大学・教授を経て現職
精神分析協会・正会員
2010年、精神分析学会山村賞受賞